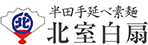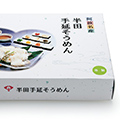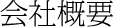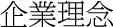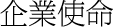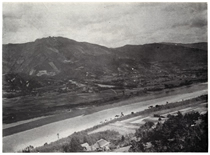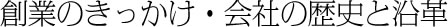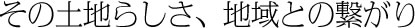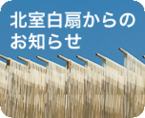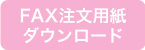売れ筋商品
トップ > 会社概要
- 社名
- 有限会社 北室白扇
- 主な取引先
- 株式会社愛晃、三井食品株式会社関西支社、三井食品株式会社九州支社、株式会社ハーベスト、首都高速道路サービス株式会社、郵便局物販サービス株式会社、株式会社日本百貨店、株式会社五味商店、ディアンドデパートメント株式会社 他
- 主な事業内容
- 半田手延べそうめんの製造・販売
手延べそば、うどんの製造・販売
その他食料品・飲料水の販売 - 所在地
- 〒779-4401
徳島県美馬郡つるぎ町半田字松生108番地5
URL https://www.kitamuro.co.jp - 業種分類
- めん類製造業
- 創業年月日
- 1977年(昭和52年)4月1日
- 法人設立年月日
- 1981年(昭和56年)7月15日
- 代表者名
- 北室 サキ
- 従業員数
- 8名(常時4名・パート4名)

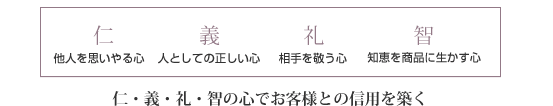

初代、北室浅太郎(あさたろう)が婿養子となり、北室家に入ったのが昭和5年。半田そうめん発祥の地・小野浜(おのはま)近く、竹田家に生まれた浅太郎は、北室家が吉野川沿いの川風が吹く良好な立地にあったことから、そうめん製造をしていた生家で身に付けた製麺技術を生かそうと、妻キヨ子と昭和7年頃「北室そうめん製造所」を始めたことがきっかけ。 昭和の初め、半田漆器の製造と販売の総元締めだった豪商「敷地屋(しきじや)」が跡取りを早くに失い、それまで半田の基幹産業だった漆器に陰りが見え始めていました。 半田漆器に代わる産業を作ろうと、当時町長だった、逢坂左馬之助(おおさか さまのすけ)氏をはじめ町の先賢らが、江戸時代から細々と行われていた手延べそうめん作りに目をつけ、推進しようとする動きが出てきました。その頃、町の後押しを受け、初代の浅太郎も播州(兵庫県揖保地方)への視察研修にも参加していました。 浅太郎がおこなっていたそうめん作りは、母屋と納屋の間を使って製造、気温の低い秋から春先までに行うもので、冷温で一定温度に保たれやすい床下で麺を熟成し、庭先でそうめんを延ばすという「天日干し」。農業の傍ら行う、当時の生産家らしいものでした。 その後、戦時下となって、度々浅太郎が兵役に招集されることになり、昭和12年にはそうめん製造の機械を金属供出し、半田そうめんの製造を中断。終戦後、無事に帰還するも、手元には機械や道具もなかったことから、そうめんの製造をすぐには再開とはなりませんでした。 昭和40年代後半に、二代目となる長男・哲男の妻、サキが浅太郎の実家のそうめん製造を助け、製麺の技術を習得。親類縁者の助けもあり、再び北室家でのそうめん製造を目指すことに。昭和51年~52年にかけて、念願の工場を新設。製造所名を「半田手延べ素麺 北室白扇工場」として、同52年4月に創業しました。昭和56年には、法人となり、社名を「北室白扇工場」から「有限会社北室白扇」に改称し、現在に至ります。
創業に際し、製麺所の名称(屋号)とトレードマークを決めることとなり、分家の北室正一(しょういち)氏が得意分野だろうとお願いすることとなりました。
製麺所の名称、北室白扇の北室は私達の名字から、白扇は白をそうめんそのものとして、扇はそのそうめんを通して、幸せが末広がりに広がりますようにとの願いを込めたもので、あえて北室「製麺」と名乗らないことにしたほどの、こだわりようがありました。
北室正一氏の父は、京都高等工芸学校(現:国立京都工芸繊維大学)図案科の第一期生。京都の染織試験場のろうけつ染め技師、泉州毛布輸出用デザインの図案家、その後、母校や同志社女子専門学校で教鞭を取るなどしていた「北室清一郎(画号:聴雪)」という人で、地元半田では、日本画家として於安御前地蔵寺(おやすごぜん じぞうじ)に「於安御前縁起絵馬」の奉納画、デザイナーとしては、町立半田小学校の校章のデザインを残している人物です。
正一氏は、自ら名付けた「北室白扇」の名に見合うよう、父から受け継いだデザイン手法を用いて、扇に北を真ん中に、小麦の穂を両脇に白扇を配した手描きデザインを制作。
のちに、「このマークと屋号をお前たちにやるのではなかった」と、弊社社長に悔やんで零すほど、氏自身、お気に入りの社名とマークであったことを申し添えます。


 北室正一
北室正一
江戸時代に、吉野川を行き来する川船の船頭衆が、そうめん作りの技術を伝えたとされるのが半田そうめんの始まりです。川港は、油や塩も比較的手に入れやすいこともあり、船頭衆の自給用や農閑期の農家の副業として作られ始めたのをきっかけに、町内に徐々にひろがっていきました。 急峻な土地が多く、平らな土地はほとんど見られません。半田という名前の通り、特にこの辺りは稲作をすることが難しかったところで、そのような土地だったからこそ、加工品のそうめん作りがこの地に根付いたと考えられています。 四国第二の高峰・剣山の麓の町らしく、冬には雪が積もる冷温湿潤な気候となっています。そのおかげで、適度な湿気を保ちながら、低温でじっくりと麺を熟成させることができます。吉野川の川風や豊富な水資源に恵まれていることとあわせて、麺作りには最適な地となっているようです。 町が産業として育てようとする機運があったこと、漆器業から職人気質を持った人が転業して出発点を支えてくれたこと、隣の県の讃岐の麺文化と接していることで、麺を楽しむ気風や半田の個性としての「太さ」が生まれたことは、半田そうめんが恵まれた点です。 今日まで半田そうめんが続いてこられたのは、先人の知恵と努力のおかげであることを忘れないでいたいとの思いで、半田素麺を知って楽しんでいただく「そうめんナイト」や半田漆器を残そう、伝えようという「オンリー椀 半田素麺編」などのプロジェクトを続けています。
- 1. 吉野川のカヌー(Trip四国の川の案内人 牛尾健さんのアウトドアツアー)
- 徳島を東西に横たわる雄大な吉野川にまっすぐ落ちていく夕陽が、鏡のような水面に映るサンセットカヌーがおすすめです。陸路(国道)や鉄道ができる明治大正まで、吉野川が「道」だったことを感じることができます。
- 2. 剣山(標高1955m)
- 四国の第二の高峰「剣山」は、つるぎ町がその玄関になっています。軽装登山ができる山ですので、半日くらいの時間を割いて登ってみてください。吉野川の平野部から剣山までの直線距離は短いにも関わらず、一気に1400~1500mほどを駆け上がるダイナミックな登山です。行き帰りの透き通った川の美しさにも目を見張りますが、急峻な山の上に青石の石積みをして家を建てる、この地ならではの暮らし方が垣間見えおすすめです。
- 3. 道の駅「貞光ゆうゆう館」
- つるぎ町の特産品「半田そうめんが食べられる道の駅」です。レストランにはもう一つの特産である生産量日本一の地鶏「阿波尾鶏」の料理もあります。世界農業遺産に認められた「急傾斜地農法」で作られた在来品種の野菜や雑穀、斜面地でつくられた特産の柚子やあたご柿など、季節の産物が朝早くから産直市に並びます。ここにはつるぎ町が全て詰まっている。剣山登山の行き帰りのお土産をここで買っていく人が多いのもうなずけます。